岡山・広島経済同友会幹部交流懇談会が2月3日、広島市で開催された。岡山から参加した中島義雄、加藤貞則両代表幹事ら25人は、広島駅ビル2階のホームから広島電鉄の貸切電車に乗車し、原爆ドーム前まで移動。会場となったおりづるタワーでは、小田宏史、香川基吉両代表幹事をはじめとする広島側の参加者24人が出迎えた。開会に当たって、小田代表幹事は「隣県同士、産業構造の転換や観光振興など似通った課題も多い。競合関係ではなく共創していく間柄でありたい」と挨拶。岡山の中島代表幹事も「互いに話をし、コミュニケーションを深め、より密接になることを願っている」と述べた。同タワーの運営に携わるヒロマツホールデングス(株)代表取締役会長兼CEOの松田哲也氏による「おりづるタワーに込めた思い」と題した卓話に続き、参加者らは屋上展望台やおりづる広場などタワーの施設を視察。懇親会も開かれ、交流を深めた。

交流部会(川妻利絵部会長)が1月29日に開かれ、香川基吉代表幹事をはじめ計18人が出席した。はじめに川妻部会長が「今年度の最終盤を迎えているが、2月から3月にかけてホスト役を務める担当行事がまだ多く残っている。ぜひ協力をお願いしたい」と挨拶。続いて議事に入り、「岡山・広島経済同友会交流懇談会」(2月3日)や「西瀬戸経済同友会交流懇談会」(2月13日)の開催概要などの説明があり、他地区からのお客をもてなす手順や役割分担などを確認した。2月25日に開く支店会員懇談会では、陸上自衛隊海田駐屯地の視察を計画していることも報告された。また交流部会の令和8年度事業計画(案)の説明もあった。

創業支援・事業承継委員会(今村徹委員長)とひとづくり委員会(冨山次朗委員長)は1月26日、合同委員会をハイブリッド形式で開催し、計41人が出席した。冒頭、今村委員長が、創業支援・事業承継委員会は今年度、広島の仕事づくりを活性化策について調査活動に取り組んでおり、今回は「人材確保」にスポットを当てて合同委員会の形で卓話を設定した狙いなどについて説明。株式会社ひろぎんホールディングス執行役員の木下麻子氏が講師を務め、「人口減少確定時代の持続的な企業・まちづくり~必要なのは、多様な人財にコア業務を任せる勇気~」をテーマに話し、性別・年齢・家庭事情に過度に配慮せず、やりたい仕事・成長できる仕事を任せ「全員活躍」組織をつくることの重要性などを訴えた。
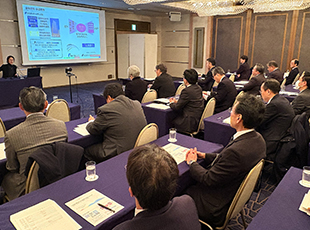
広島経済同友会は1月22日、「創立70周年記念式典」をホテルグランヴィア広島(広島市南区)で開いた。横田美香広島県知事をはじめ、(公社)経済同友会の岩井睦雄筆頭副代表幹事を含めて各地の経済同友会の代表らを来賓に迎える中、広島からも多くの会員が出席。節目となる創立70周年を祝うために総勢300人が集った。開会に当たって、小田宏史代表幹事が「70年はゴールではなく、次の10年、20年に向けた新たなスタートラインである」と挨拶。続いて創立60周年以降に代表幹事を務めた5名に特別幹事表彰を、当会会員として30年以上活躍した30名に永年会員表彰をそれぞれ授与した。記念講演では、株式会社大和総研代表取締役副社長兼副理事長調査本部長の熊谷亮丸氏が「日本経済の展望と課題」と題して話した。記念祝賀会もあった。

新年最初の幹事会が1月22日、ハイブリッド形式で開かれ、小田宏史、香川基吉両代表幹事をはじめ計86人が出席した。挨拶で小田代表幹事は、今年の干支である丙午(ひのえうま)について「勢いと冷静な判断が調和し、変化を成長につなげる年とされる」と述べ、「一歩先の成長に向けて、皆さんとともに学び挑んでまいりたい」と強調した。続いて呉など3支部と交流部会、観光振興など2委員会から昨年12月の活動と新年1月以降の行事予定の報告があり、交替10名、退会1名の会員異動を承認した。また、オール広島での連携と共創を一層強め、50年後の子どもたちに誇れる持続可能な都市の実現に向けての責任と役割を果たしていく-などとする令和8年度事業計画基本方針(案)の説明があり、了承した。

総務部会(小川裕子部会長)は1月15日、ハイブリッド形式で開催し、計15人が出席した。小川部会長は冒頭の挨拶で、今年が60年に一度だけ巡ってくる「丙午(ひのえうま)」であることに言及。「丙午の女性は気性が荒く、夫の寿命を縮める」などといった科学的根拠のない迷信があり、前回の丙午だった1966年には、出生数が大幅に落ち込むなど、社会に大きな影響を与えたことを紹介。時代は大きく変わっており、「若い人が迷信やデマなどを耳に入れず、出生率が下がることのないよう願っている」と述べた。続いて谷口康雄事務局長が12月の活動と1月以降の予定、会員異動の状況を報告。小川部会長から令和8年度の基本方針のポイントの説明などがあり、意見交換した。
